目次
電子棚札(ESL)のメリットとデメリットを徹底解説 〜 導入前に確認したい4つのポイント 〜
- 業務改善・DX
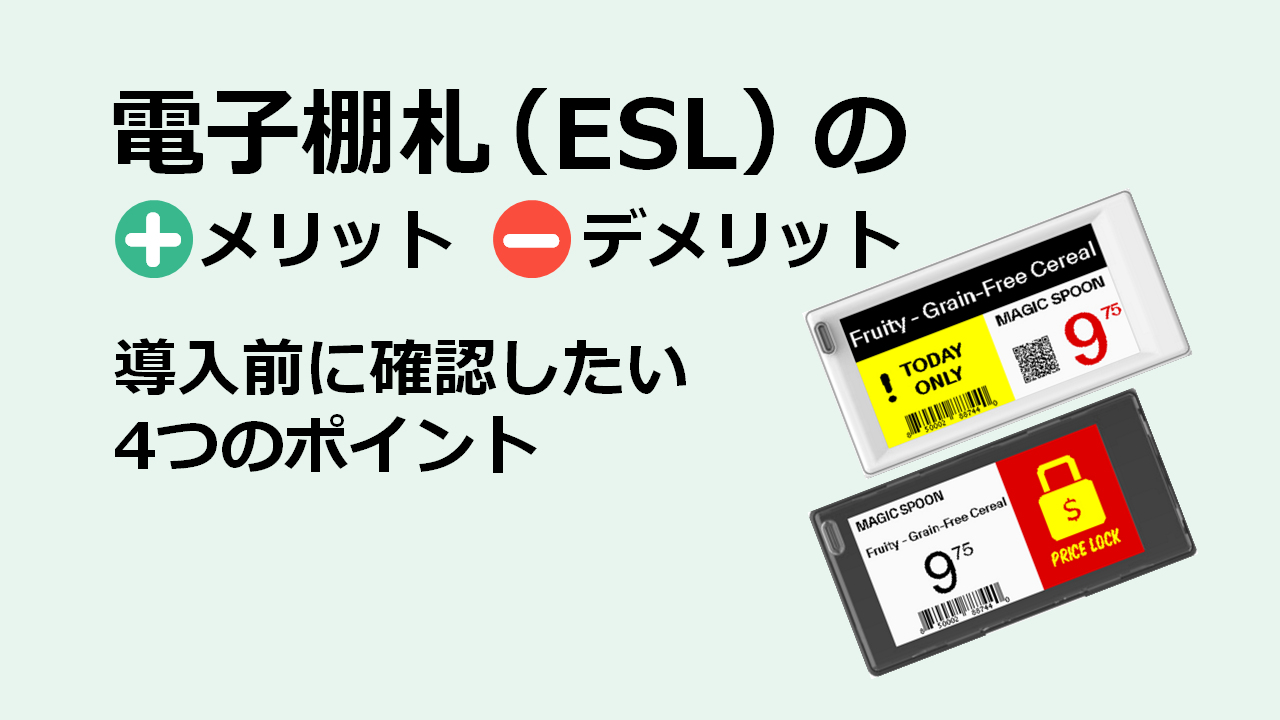
電子棚札(ESL)とは、店頭の紙の値札を小型ディスプレイに置き換え、無線で価格や商品情報を一括更新できる仕組みです。
本記事では、電子棚札のメリット・デメリットを網羅し、導入前に確認したい4つのチェックポイントをわかりやすく整理しました。ムダな投資や回収の遅れを避けるために、判断に必要な要点だけを短く整理しましたのでぜひ参考にしてください。
なお当社では、電子棚札と組み合わせることでより効率的に品質管理ができるシステム「Expiry Management(エクスパイリー・マネジメント、旧Semafor)」を提供しています。
最大90日間の無料トライアルもある「エクスパイアリーマネジメント」の詳細は、下記からサービス資料を無料ダウンロードしてご確認ください。
1. 店舗運営がラクになる!電子棚札の6つのメリット

電子棚札は、店舗運営がラクになる導入メリットが多く存在するデジタルツールです。はじめに、電子棚札の主なメリットを6つ紹介します。
メリット①:作業効率の向上
電子棚札の導入により、値札作業にかかる時間が大幅に削減されます。印刷や貼り替えといった手作業が不要になるため、浮いた人手を品出しや接客など、より付加価値の高い業務に回せます。
これは、価格や表示内容を無線で一括更新できる仕組みのおかげです。さらに、表示レイアウトをひな形化できるため、データ作成や表示内容の確認もスピーディーになります。
例えば、特売や値下げの際には、PCや端末から一括で価格を送信するだけで、売場では表示を目視確認するだけで完了します。棚替えのタイミングでもラベルを作り直す必要はなく、データを切り替えるだけで対応可能です。
このように、作業時間の短縮と手戻り防止により、現場の負担が減り、店舗全体のオペレーションがスムーズになります。
メリット②:リアルタイムでの価格変更
電子棚札なら、値下げやセール価格をすぐに反映でき、売り逃しを抑えられます。対応機種であれば、価格の反映のタイミングを時間指定でコントロール可能です。
例えば、雨天時だけ対象カテゴリを即時に値下げして来店を促す、といった運用も簡単です。価格変更のスピードが上がることで、割引のタイミングを逃すなどの機会損失が減り、販売機会の最大化につながります。
メリット③:ヒューマンエラー防止
印刷・切り出し・貼り替え・二重転記といった細かい手作業が減るため、ミスの入り口そのものを小さくできます。値札とレジ価格の不一致も減り、クレームや返金、差し替え作業を少なくすることが可能です。
更新は一度の入力で店内へ一斉に反映され、棚札に触る回数と工程が減るため、人為的なミスが起きにくい設計です。商品IDにひもづけて表示を管理できるため、設定ミスの発生も抑えられます。
例えば、類似商品の棚札を取り違えるといった差し替えミスも、貼り替え作業自体がなくなることで大幅に減らせます。結果として、是正対応の時間と顧客対応コストを同時に下げることが可能です。
メリット④:販促ツールとして活用
電子棚札を使用すると商品の魅力を伝えやすくなり、購入を後押しできます。関連商品や上位商品の同時購入・ついで買いも促せるためです。
画面上におすすめ情報やポイント施策を表示でき、QRコードでレシピやレビューなどの詳細ページへの誘導もスムーズに行えます。
具体的には、セット購入がお得なことを棚札に表示して提案したり、会員特典やクーポン情報を切り替えて掲示したりできます。結果として、客単価の向上や販促の打ちやすさにつなげられるのです。
メリット⑤:在庫・期限との連動でロス削減
電子棚札を在庫や販売期限情報と連動させると、販売期限が近い商品の売れ残りを抑え、廃棄を減らせます。見切り販売の回収率向上にもつながる設計です。
期限が迫った商品は目立つお買い得表示へ自動切り替えでき、残数や販売の動きに応じて表示内容を柔軟に変えられます。例えば、「残りわずか」の表示で買い逃しを防ぎ、対象商品の棚位置がすぐわかるようにすれば、見切り作業もスムーズに進みます。
なお、賞味期限のある商品の管理にはExpiry Management(エクスパイリー・マネジメント、旧Semafor)の活用が有効です。商品ごとの期限を入力するだけで販売期限を監視し、期限が迫った商品を自動で告知できます。
廃棄ロスの削減と業務効率化を求める場合は、下記からサービス資料を無料ダウンロードしてご確認ください。
メリット⑥:サステナビリティへの貢献
電子棚札に切り替えると紙とインクの使用量を大幅に削減できます。廃棄ロスの抑制とも相まって、環境負荷の低減に寄与します。紙媒体をデジタルに置き換えること自体が、二酸化炭素排出量の削減につながるからです。
例えば、値札印刷をゼロにして差し替えごみを出さない運用へ移行し、特売終了時も配信で表示を戻すだけにすれば、紙資材は不要です。期限連動で売り切りを進めれば、食品廃棄の削減にも寄与できます。
ここまで、電子棚札のメリットを6つ紹介しました。続いて、実際に導入する前に知っておきたいデメリットも確認しましょう。
2. 導入前に知っておきたい電子棚札の3つのデメリットや注意点

電子棚札の主なデメリットや注意点は、次の3つです。
対策とあわせて紹介しますので、自社で導入すべきかのご参考になさってください。
注意点①:初期費用がかかる
電子棚札は、端末やゲートウェイの購入・設置、ソフトウェア利用料、保守費など初期投資が比較的大きいため、費用負担を重く感じやすいのが実情です。
まずは値替え頻度の高い売場から小さく始め、効果を数値で確認しながら段階的に拡大すると無理がありません。月々払いの活用や公的支援の併用で支払いを平準化し、キャッシュフローへの影響を抑える方法もあります。
注意点②:電波が届きにくい場所がある
店舗形状や金属棚、冷蔵・冷凍ケースの影響で電波が届きにくく、反映の遅れや表示のばらつきが生じる場合があります。
導入前に店内の電波状況を可視化し、届きにくいエリアは基地局の追加や配置見直しで解消できます。冷蔵・冷凍周りの安定運用には、低温対応の札とアンテナ位置の工夫が鍵です。
店舗形状や金属棚、冷蔵・冷凍ケースの影響で電波が届きにくく、反映の遅れや表示のばらつきが生じる場合があります。
導入前に店内の電波状況を可視化し、届きにくいエリアは基地局の追加や配置見直しで解消できます。冷蔵・冷凍周りの安定運用には、低温対応の札とアンテナ位置の工夫が鍵です。
注意点③:電池交換や機器の手入れが必要になる
電池式タグには寿命があり、更新頻度・温度環境・機能の使い方によって消費速度が変わります。そのため、点検・交換の作業負担が発生し、放置すると表示停止につながるリスクがあります。
対策としては、電池残量を一覧で把握し、残量の少ないものは早めに交換する運用へ切り替えるなどです。更新が多い売場は省電力設定や長寿命モデルの採用で負担を抑え、計画的にメンテナンスすることも有効です。
3. 失敗しない!電子棚札の導入前にチェックしたいこと4選

続いて、電子棚札の導入前に注意すべきチェックリストとして、下記4つの項目を確認してみましょう。
チェック①:収支はプラスになりそうか
まずは自店の数字で導入後の見通しを立てることが大切です。そのためには、効果検証の基準線(ベースライン)になる現在の実績を可視化しておく必要があります。
実績を洗い出す一例は、次のとおりです。
● 現在の値札作業にかかっている時間
● 紙とインクにかかっている月間コスト
● 価格不一致や廃棄の発生件数・金額
短期レンタルや小規模パイロットで小さく試す期間を設定し、開始前と終了後で次の項目を同条件で測定します。
● 作業時
● 不一致件数
● 廃棄率
最後にリース費用などを含めた差分を金額換算して比較すれば、収支がプラスになるかを定量的に判断できます。
チェック②:価格の変更が店内で確実・速やかに反映するか
電子棚札と基地局の通信が確実に届き、素早く反映されるかを実地で確認してから導入を決めましょう。
まず、金属棚や冷蔵・冷凍ケース、柱の陰など電波が弱くなりやすい場所を売場マップに書き込み、テスト用の棚札を難所に仮固定して同時更新を繰り返します。反映が遅い、または届かない箇所があれば、基地局の追加や配置の見直しで改善しましょう。
さらに営業日、開店前、繁忙帯といった異なるタイミングで動作を確認しておくと、本番運用時の想定外を減らせます。
チェック③:毎日の運用が手間なく回るか
導入がうまくいく店舗は、表示のひな形と確認の順番を先に決めています。総額表示・単価表示・軽減税率の表記を一枚のテンプレートにまとめ、誰がいつ承認するかまでマニュアル化しておくと、日々の更新が滞りません。
併せて、次の点を事前にルール化しておくと、運用の安定性がさらに高まります。
● 朝夕の時刻指定での切り替えができるか
● 停電時に表示はどう残るか
● 復旧はどうするか
これらを先に決めておくと現場が迷わずに回り、トラブル発生時も短時間でリカバリーできます。
チェック④:困ったときのサポートがあるか
トラブル発生時に最初の連絡先が一本化され、受付から解決まで同じ窓口が責任を持って伴走してくれる体制だと安心です。
電子棚札は、ハード機器、無線や基地局、設置工事、管理ソフトで担当が分かれがちですが、ワンストップの窓口があれば困りごとの解決がスムーズに進みます。導入したいサービスに、どのようなサポートがあるかを把握しておきましょう。
まとめ|電子棚札で作業時間とミスとロスを減らそう

電子棚札は、作業効率の向上やリアルタイムでの価格変更、ヒューマンエラー防止、販促や在庫管理への活用、サステナビリティへの貢献など、店舗運営に多くのメリットをもたらします。一方で、初期費用や通信環境、電池交換といった課題もあるため、導入前にしっかりと検討することが大切です。
本記事で紹介したチェックポイントを踏まえ、自店に合った規模・タイミングで導入を進めれば、現場の負担を減らしながら収益改善も可能です。貴社の課題が「作業時間・ミス・廃棄ロス」の削減なのであれば特に、電子棚札という専用ソリューションの導入をご検討ください。

なお当社では、電子棚札とあわせて賞味期限チェックを自動化できるシステム「Expiry Management(エクスパイアリーマネジメント、旧Semafor)」も提供しています。品質管理や廃棄ロス削減をさらに進めたい方は、ぜひサービス資料をご覧ください。
「Expiry Management(エクスパイリー・マネジメント、旧Semafor)」は、賞味期限管理に特化したデジタルツールです。
商品ごとに賞味期限を入力するだけで販売期限を自動モニタリングし、期限が近づいた商品をスタッフへ即座に通知します。これにより、チェック作業の負担を大幅に軽減し、廃棄ロスの削減にもつながります。
この記事を書いた人
whywaste-japan


