目次
電子棚札の本体価格と導入・運用コストを徹底解説! 〜 「SESimagotag」で効率的な店舗運営を実現 〜
- 業務改善・DX
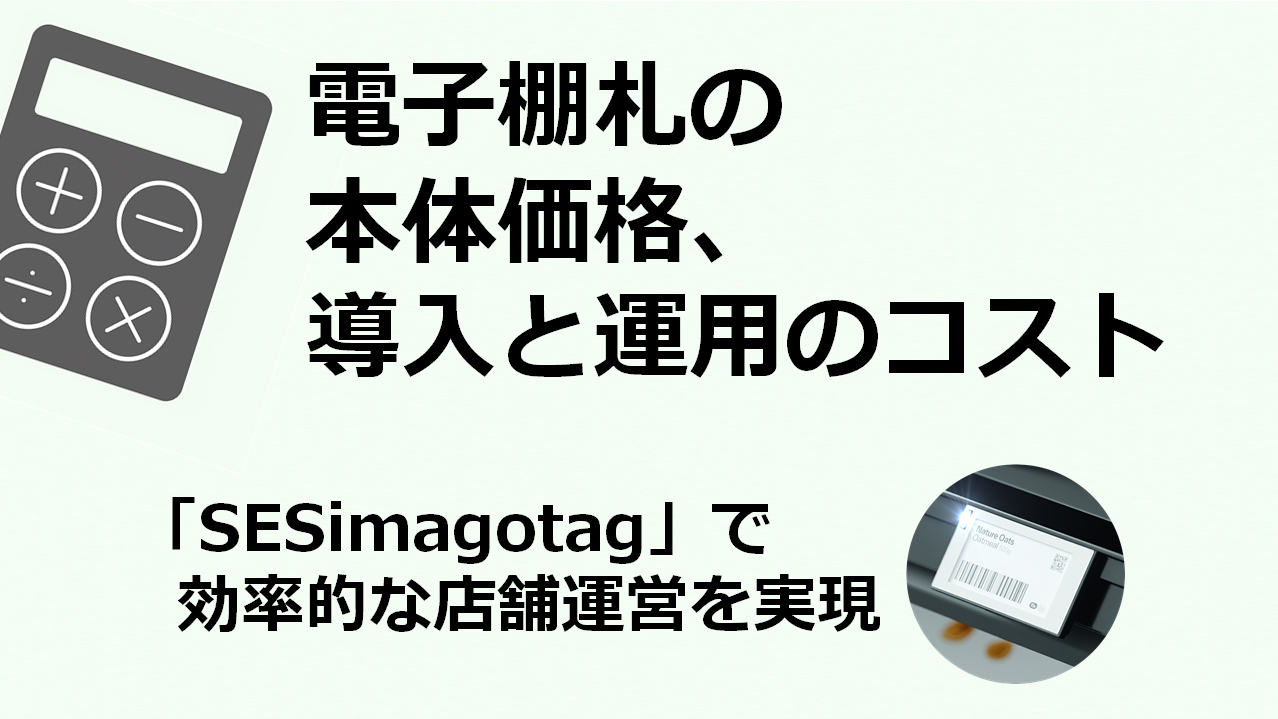
店舗運営において頻繁に発生する価格変更作業。これを効率化できる電子棚札(ESL:Electronic Shelf Label)の導入が、近年多くの小売・流通業で進んでいます。
電子棚札は業務効率化や人件費削減、誤表示防止などのメリットがありますが、やはり気になるのは費用面ではないでしょうか。
本記事では、電子棚札の価格相場や導入に必要な費用について解説するとともに、コスト削減のポイントもご紹介しています。ぜひ導入検討の参考にしてください。
1. 1枚あたりの電子棚札の価格相場は?

電子棚札を導入する際、まず気になるのが「1枚あたりの本体価格」です。本体価格はサイズや機能によって異なり、数千円〜数万円と幅広くあります。
ここでは代表的なサイズを3つに分類し、それぞれの特徴や価格の目安を紹介します。
| サイズ | 本体価格の目安 |
|---|---|
| 小型(約1.5〜2.5インチ) | 1,000〜3,000円程度/枚 |
| 中型(約3〜5インチ) | 2,000〜8,000円程度/枚 |
| 大型(約6インチ以上) | 8,000〜50,000円程度/枚 |
小型(約1.5〜2.5インチ)
小型タイプは、主に商品価格やバーコードなど、基本的な情報だけを表示するのに適したシンプルなものです。価格は1枚1,000〜3,000円程度と導入しやすく、試験的に運用を始める場合にもおすすめです。
小型なので、調味料ボトルやレジ周りなど、スペースが限られた場所での利用に向いています。歯ブラシなど、ぶら下げて陳列するフック什器の先端にも設置可能です
中型(約3〜5インチ)
中型タイプは、通常の商品価格だけでなく、割引価格や在庫数を同時に表示できるようになっています。価格は1枚2,000〜8,000円程度となっており、文字サイズを大きく表示できるので、視認性が良くなります。
アパレルや家電量販店など、棚幅が広く、商品情報を詳しく表示したい場合にも使われています。
大型(約6インチ以上)
大型タイプは、商品価格だけでなくスペック比較、在庫情報、QRコードなど、商品情報を多く表示できます。価格は1枚8,000〜50,000円程度と幅広く、カラー表示やLED点滅といった付加機能の有無によって変わります。
商品の写真や特徴などを盛り込めば、POPとしても利用可能で、プロモーションにも最適です。
2. 電子棚札の導入に必要な初期費用

など、初期費用はトータルで数十万円〜数百万円になるケースもあるので、事前確認が必要です。ここでは、代表的な初期費用を紹介します。
| 初期費用の内訳 | 導入費用の目安 | 備考 |
|---|---|---|
| 1.PDA端末の費用 | 5〜6万円程度/台 | |
| 2.アクセスポイントの費用 | 2〜5万円程度/台 | |
| 3.サーバー構築・クラウド利用の費用 | (構築)数十〜数百万円 (クラウド利用)月額2〜3万円 | 導入方式や規模による |
| 4.自社システムとの連携費用 | 規模や条件などによって費用は変動する | ・連携範囲による ・サーバー構築費と合わせて算出される場合あり |
| 5.工事・設定費用 | 規模や条件などによって費用は変動する | ネットワーク環境や電子棚札の台数、レイアウトなどによる |
| 6.電波干渉チェック費用 | 規模や条件などによって費用は変動する | 店舗の広さや通信環境による |
1.PDA端末の費用
PDA(Personal Digital Assistant)端末は、電子棚札と商品データを紐づけたり、設定や管理をするための端末です。価格は1台あたり5〜6万円前後が目安になります。
1台でも運用可能ですが、中規模店舗の場合、数台用意しておくと、スタッフが同時に作業できるので効率的です。
商品が少ない場合は、手動で紐づけをする場合もありますが、効率化のためには導入をおすすめします。
2.アクセスポイントの費用
電子棚札は、Wi-FiやBluetoothなどの無線通信で商品情報を受け取るため、店舗内にアクセスポイント(中継器)が必要になります。
価格相場は1台あたり2〜5万円程度で、1つのアクセスポイントでカバーできる範囲は、半径20m〜30mほどが目安です。そのため、売場が広い店舗では複数台必要になるケースが一般的です。
3.サーバー構築・クラウド利用の費用
電子棚札を管理するシステムを動かすには、サーバーが必要です。自社サーバーを設置する「オンプレ型」(オンプレミス(on-premises)の略)と、外部のサーバーをインターネット経由で利用する「クラウド型」の2種類があります。
それぞれの費用と特徴は、下記のとおりです。
| 種類 | 費用と特徴 |
|---|---|
| オンプレ型 | 初期費用が高め。数十万〜数百万円規模になる場合も。 外部のネットワークに依存しないので、セキュリティ面を強化しやすい。 |
| クラウド型 | 初期費用を抑えられる一方で、月額2〜3万円程度の利用料がかかる。 複数店舗を一括管理できる点がメリット。 |
4.自社システムとの連携費用
価格を表示するだけではなく、電子棚札を自社システムと連携させると、さらに業務の効率化につなげられます。
例えば、
・在庫データを自動で電子棚札に反映する
・POSの販売実績に応じて価格を自動変更する
という使い方も可能です。
連携する場合は、追加の開発・設定費用が必要になります。費用は、システムの規模や仕様によって大きく異なりますので、事前にベンダー(販売会社)に見積もりを依頼しましょう。サーバー構築費と合わせて算出される場合もあります。
5.工事・設定費用
店舗内で電子棚札を取り付ける工事や、システム設定を行うためには、別途費用がかかります。ネットワーク環境や初期設定の範囲、電子棚札の台数、レイアウトなどによって価格は変動します。
6.電波干渉チェック費用
電子棚札は無線通信を利用するため、Wi-FiやPOSレジなど、既存の無線機器と干渉しないか、事前に確認する必要があります。特に大型店舗や家電量販店のような、無線機器が多い環境では必須です。
トラブル防止のため、導入時にまとめて行うのが一般的で、費用は店舗の広さや通信環境によって異なります。
3. 電子棚札の運用にかかる費用

電子棚札を導入する際、初期費用だけでなく、継続して運用するためのランニングコストについても考えなければいけません。
特にサーバー利用料や保守・サポート、電池交換といった費用は、長期的なコストに影響します。ここでは代表的な運用費用を紹介します。
| 初期費用の内訳 | 導入費用の目安 | 備考 |
|---|---|---|
| 1.サーバー利用料 | (クラウド型)2〜3万円程度/月 | ハード保守費用が含まれることが多い |
| 2.保守・サポート費用 | 3〜4万円程度/月 | 店舗の規模や契約内容による |
| 3.電池交換やメンテナンスの費用 | (電池)数百円/枚 (メンテナンス)範囲による | 電池は「保守・サポート費用」の中に含まれる場合もあり |
1.サーバー利用料
複数店舗をまとめて管理できるクラウド型を利用した場合、月額2〜3万円程度の利用料が発生します。多くの場合は、この中に電気代やハード保守にかかる料金も含まれています。
オンプレ型にはサーバー利用料は発生しませんが、電気代や保守費用、管理人件費が別途必要です。そのため、オンプレ型の場合は、中長期的な運用負担を見込む必要があります。
2.保守・サポート費用
導入後も、システムの安定運用やトラブル対応には、保守・サポート契約が欠かせません。
月額3〜4万円程度が相場で、サービス内容には定期点検や不具合対応、システム更新などが含まれます。
店舗の規模や契約内容によって費用は変動しますが、安心して運用するためには必要なコストといえます。
3.電池交換やメンテナンスの費用
電子棚札はボタン電池で駆動するタイプが多く、寿命は3〜6年程度が一般的です。電池交換の際は、1枚あたり数百円のコストが発生し、大型店舗の場合は、交換時に数万円単位の費用がかかる場合もあります。多くの場合は「保守・サポート費用」の中に含まれています。
また、表示部の劣化や防水・防塵性能のチェックなど、軽微なメンテナンスも必要です。ランニングコストとして、定期的に発生する点を考慮しておくと安心です。
4. 電子棚札の費用対効果を考える

電子棚札は初期費用が大きいため、「本当に元が取れるのか?」と不安に感じる方も多いのではないでしょうか。
初期費用の金額だけを見るのではなく、長期的な人件費や効率化などを考慮し、総合的な判断をする必要があります。
ここでは、紙の棚札との比較や業務効率化の効果、費用回収の目安について考えます。
1.紙の棚札との比較
格変更のたびに新しい棚札を印刷し、スタッフが差し替える作業が発生します。
電子棚札は導入時のコストがかかりますが、長期的には印刷費や交換作業が不要になり、運用コストは電池交換や保守費用などに限定されます。長期的に見ると、電子棚札のほうがコストを抑えられるケースが多くなっています。
2.業務効率化・人件費削減の効果
紙の棚札では、価格変更作業を行う場合、スタッフが1枚ずつ差し替える必要があります。数百点の商品が対象となると、数時間に及ぶ作業になりかねません。
電子棚札なら、パソコンやタブレットから一括更新できるため、作業時間を大幅に削減できます。浮いた時間を接客や売場改善に向けられるだけでなく、棚札の付け間違いなどのヒューマンエラーも防止できるのです。
誤表示によるクレームや、価格差異の損失を防げるメリットを考えると、コスト削減以上の効果が期待できるといえます。
3.費用回収の目安と導入判断の基準
電子棚札の費用回収については、導入規模のほか、下記のようなポイントを踏まえて判断する必要があります。
【電子棚札の費用回収判断ポイント】
- 価格変更の頻度
- 人件費の水準
- 棚札の枚数
- システム連携による追加効果(在庫管理や販促連携など)
- 電池寿命や保守点検などの運用コスト
例えば、価格変更が頻繁でスタッフの作業時間が多い店舗では、人件費削減の効果が大きく、回収期間が短くなる傾向があります。
また、在庫管理システムや販促アプリと連携させれば、単なる価格表示以上の効果を得られる場合もあるのです。
追加メリットも加味すれば、導入判断の精度が高まり、投資効果をより正確に見積もれるようになります。
5. 電子棚札の導入費用を抑える方法

電子棚札のメリットや効果について理解できても、やはり費用面のハードルは高く感じるものです。ここでは、導入費用を抑えつつ効果を確認できる、代表的な3つの方法を紹介します。
方法1. 試験導入して効果を検証する
方法2. 紙と電子を併用する
方法3. レンタルプランを活用する
方法1. 試験導入して効果を検証する
初めから全店舗・全売場に導入するのではなく、まずは売場の一部や特定カテゴリに限定して導入し、効果を検証する方法です。
例えば、価格変更が多い惣菜コーナーや日用品売場で使ってみると、業務量の軽減を実感しやすくなります。また、複数店舗ある場合は1店舗だけ導入し、他店舗と比較してみるという方法も有効です。
小規模導入なら投資額も抑えられるため、費用対効果を見極めたうえで全体導入に進めます。
方法2. 紙と電子を併用する
すべての商品を電子棚札に変えるのではなく、一部の売り場にだけ導入し、他は紙の棚札を使用する方法です。
初期投資を抑えながら効率化も実現でき、さらにそれぞれの強みを活かした使い方ができます。
例えば、
・価格変更の頻度が高い売場は電子棚札を利用
・特売品や目玉商品には、感情的訴求に強い手書きPOPと紙の棚札を併用
という使い分けもできます。
方法3. レンタルプランを活用する
ベンダーによっては、電子棚札をレンタル形式(月額課金)で提供している場合もあります。初期費用を抑え、少数から利用できるので、試験導入やシーズン限定の利用などにも適しています。一度に大きな投資をせずに効果を試したい場合におすすめです。
電子棚札だけの利用料金の目安は、下記のとおりです。
【サイズ 1枚あたりのレンタル費用/月】
- 小型 : 50 〜 200円
- 中型 : 160 〜 350円
- 大型 : 1000円 〜
費用対効果の高い電子棚札なら「SESimagotag」がおすすめ

電子棚札の導入には初期費用や運用コストがかかりますが、作業の効率化や人件費削減、誤表示防止など、メリットは多くあります。
特に価格変更が頻繁に発生する店舗では、紙の棚札よりも高い費用対効果が期待できるのです。
さらに電子棚札は単なる価格表示だけでなく、在庫管理や販促システムとの連携によって、店舗全体の運営改善にも効果的です。
特に世界トップシェアを誇る「SESimagotag」は、賞味期限管理アプリと連携すると、廃棄ロスの削減が行えます。
また、カスタマーレビューやデジタルクーポンなどを表示して、顧客満足度の向上も実現可能となっています。
【関連記事】“仕組み化”で変わる!賞味期限管理の改善レシピ【現場で使える5つの具体策】
電子棚札の導入を検討する際は、費用対効果を考え、自社にとっての投資効果を見極めることが大切です。
費用対効果の高いソリューションをお探しなら「SESimagotag」をぜひご検討ください。具体的な導入事例やお見積もりについては、下記の資料でご確認いただけます。

なお当社では、電子棚札とあわせて賞味期限チェックを自動化できるシステム「Expiry Management(エクスパイアリーマネジメント、旧Semafor)」も提供しています。品質管理や廃棄ロス削減をさらに進めたい方は、ぜひサービス資料をご覧ください。
「Expiry Management(エクスパイリー・マネジメント、旧Semafor)」は、賞味期限管理に特化したデジタルツールです。
商品ごとに賞味期限を入力するだけで販売期限を自動モニタリングし、期限が近づいた商品をスタッフへ即座に通知します。これにより、チェック作業の負担を大幅に軽減し、廃棄ロスの削減にもつながります。
この記事を書いた人
whywaste-japan


