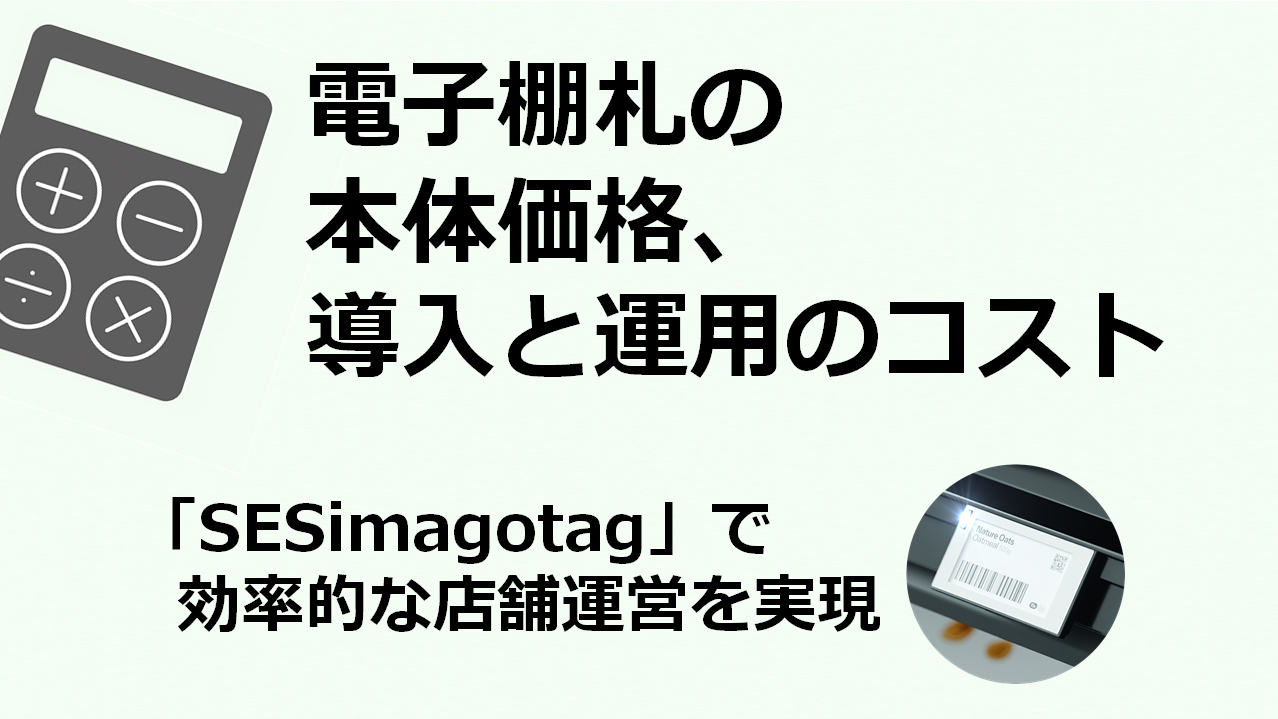目次
統合システムでは限界? 賞味期限管理に特化した専用ツールの強み
- 業務改善・DX賞味期限管理Labs
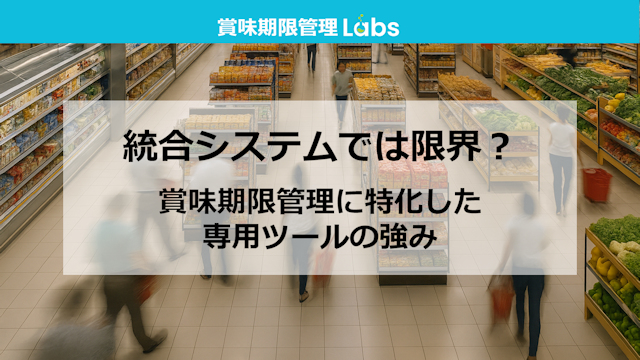
店舗DXが進むなかでも、現場で最後まで残されている“アナログ作業”があります。それが「賞味期限管理」です。
人手不足や最低賃金の上昇、食品ロス削減の社会的要請が強まるいま、手作業に依存したままでは限界が見えてきました。
この記事では、統合システムではカバーしきれない課題と、専用ツールならではの強みを、事例や比較を交えて解説します。
1. 賞味期限管理が「最後のアナログ領域」と言われる理由
理由①:在庫管理・発注はDX化が進む一方で残る課題
小売業界ではここ数年、需要予測AIや自動発注、在庫最適化などを取り入れた「店舗DX」が加速しています。POSデータを活用した仕入れ・在庫管理は一般化し、効率的な運営体制が整いつつあります。
一方で、最低賃金の上昇や人手不足といった課題が深刻化するなか、現場で依然としてアナログ作業に頼っている領域があります。それが「賞味期限管理」です。
在庫数がどれだけ正しく最適化されても、売場の商品一つひとつの期限を把握できなければ、廃棄ロスは避けられません。つまり、統合システムが得意とするのは「量の管理」であり、「時間の管理=賞味期限管理」は別のアプローチを必要としています。
さらに、ESG経営や食品ロス削減への社会的要請が高まる今、賞味期限管理の効率化は単なる業務改善にとどまらず、企業の持続可能性を左右するテーマとなっています。
理由②:現場スタッフに依存する賞味期限チェックの実態
多くの店舗では、以下のような運用が続いています。
- ◎ スタッフが棚を回り、商品を一つひとつ手に取り期限を確認
◎ 期限が近い商品を手書きリストやExcelに記録
◎ 値引きや廃棄判断を、現場スタッフの裁量で行う
この流れには多くの問題があります。
- ◎ 時間がかかる(1店舗あたり1日数時間かかるケースも)
- ◎ 人的ミスが避けられない(見落とし、記録ミス、作業忘れ)
- ◎ 作業が属人化(ベテランに頼らざるを得ない)
つまり、「システムで発注・在庫は管理できても、期限チェックだけは現場スタッフの目と手に頼るしかない」という現状が続いているのです。
理由③:本部と現場では、見ている情報の“種類”が違う
✅ 本部の立場
本部はシステム上の「在庫数」や「売上データ」をもとに管理をしています。
数字で全体像を把握し、在庫最適化や発注量の調整を行います。
✅ 現場の立場
一方、店舗スタッフが見ているのは「棚に並んでいる実際の商品」です。
期限が近づいている商品に値引きシールを貼ったり、処分せざるを得ない商品を廃棄したりするのは現場の仕事です。つまり、数字ではなく“現物とその期限”を直接扱っています。
2. 統合システムでは賞味期限管理が難しいワケ
📌 1. 在庫・発注システムの目的は「在庫最適化」
統合型の在庫・発注システムは、販売予測をベースに「在庫量の最適化」を目的としています。
つまり、システムの軸はあくまで数量の管理。商品一つひとつの「期限」という時間軸までは、十分に踏み込めていません。
📌 2. 期限管理機能は付加的で使われにくい
統合システムの中には賞味期限を入力できる機能を持つものもあります。
しかし、実際には「付加機能」にとどまり、次のような課題が目立ちます。
- ◎ 期限データの入力が煩雑で、作業負担が増える
- ◎ 画面構成やインターフェースが複雑で、直感的に使いづらい
- ◎ 本部向けに設計されており、現場の作業手順に沿っていない
結果として「機能はあるが現場で活用されない」というケースが少なくありません。
📌 3. 現場のチェック作業に適応していない
賞味期限管理は、現場で「棚を回りながら商品を確認する」作業です。
しかし多くの統合システムは、デスクでの入力や帳票管理を前提に設計されています。
- ◎ 棚の前でスマホや端末を片手に素早く操作できない
- ◎ 現場スタッフが一日に何十回も繰り返すチェック作業に合わない
つまり、現場のオペレーションとシステム設計の間に大きなズレがあるのです。
📌 4. 「現場ファースト」になっていない仕様
本部にとっては便利でも、現場にとっては不便――これが統合システムの限界です。
本部は「数字上の在庫」を見ていますが、現場は「売場に並ぶ商品とその期限」を扱っています。
本部主導で作られたシステムでは、現場で求められる「スピード」「簡単さ」「確実性」を満たせないのです。
3. 賞味期限管理に特化した専用ツールの強み
💡 シンプル操作で誰でも正確にチェック可能
☞ 専用ツールの大きな特徴は、「誰でも」「すぐに」使えるシンプルな操作性です。
- ◎ バーコードをスキャンするだけで期限が一覧化
- ◎ 期限が迫った商品をアラートで通知
- ◎ 値引きや廃棄の判断基準を自動表示
💡 作業時間を最大80%削減
☞ 従来は数時間かかっていたチェック作業が、わずか数十分に短縮された事例もあります。人件費が高騰する中、作業工数を大幅に減らせることは経営に直結する効果です。
💡 廃棄ロスを最大40%削減
☞ スウェーデンをはじめとする海外の事例では、専用ツール導入によって廃棄が30~40%削減されたと報告されています。単にコスト削減だけでなく、ESG経営やSDGsの観点でも重要な成果です。
💡 既存システムと競合せず、むしろ補完する
☞ 在庫・発注の「量」の管理に対して、専用ツールは「時間」の管理を担います。両者を組み合わせることで、初めて 「売場全体の最適化」 が実現するのです。
4. 実際の導入事例から見る効果
✅ スーパーでの新人スタッフでもできる管理体制
専門知識がなくても操作できるUI設計により、新人スタッフでも初日から正確に期限チェックが可能となりました。属人化を防ぎ、教育コストも下がりました。
✅ 大手ドラッグストアでの人件費削減と効率化
チェーン展開するドラッグストアでは、店舗ごとに人件費負担が課題でした。専用ツール導入により、期限チェック作業が大幅に短縮され、スタッフを接客や売場改善に回せるようになりました。
✅ 空港や土産物店における少人数運営の支援
観光施設の土産物店では、数人のスタッフで多品種の商品を扱う必要があります。専用ツールにより、限られた時間で効率的に期限管理を行い、廃棄ロスを最小限に抑えています。
5. 統合システム vs 専用ツール 比較表
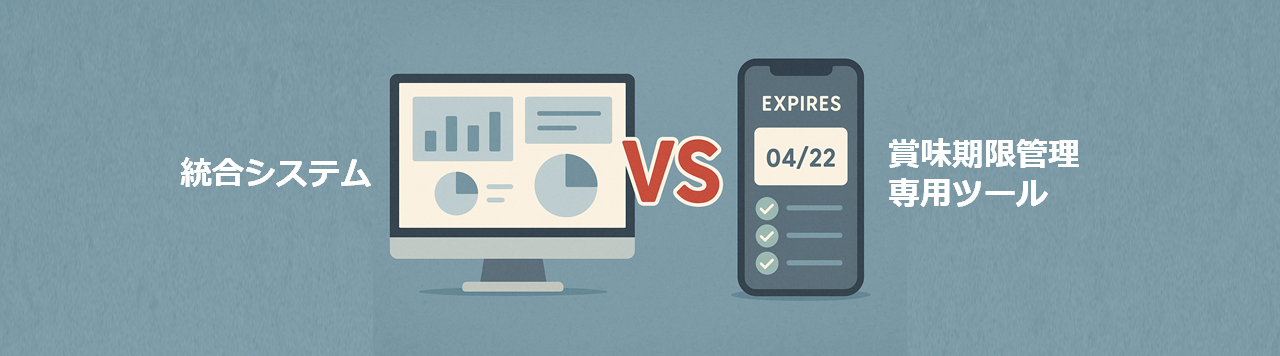
賞味期限管理を改善するには、統合システムに機能を持たせるのか、それとも専用ツールを導入するのか、という選択肢があります。
ここでは「導入のためのコスト・期間」「ランニングコスト」「運用のしやすさ」「効果の出やすさ」といった観点で比較してみましょう。
| 項目 | 統合システム | 専用ツール(賞味期限管理特化) |
|---|---|---|
| 導入コスト | 数百~数千万円規模 | 低コスト(月額のアカウント料金) |
| 導入準備期間 | 半年~1年以上(要カスタマイズ・社内調整) | 数週間~数か月(クラウド利用で短期導入可) |
| ランニングコスト | 高め(保守料+追加機能料) | 比較的低い(月額利用料中心) |
| 機能範囲 | 広い(発注・在庫・棚割など全体最適化) | 特化(賞味期限チェック・値引き・廃棄管理) |
| 現場適合度 | △(本部目線の設計が多く、現場では使いづらい) | ◎(棚前で直感的に操作可能、現場ファースト設計) |
| 作業効率化 | △(期限管理は補助的な位置づけ) | ◎(チェック作業を最大80%削減) |
| 廃棄ロス削減効果 | ◯(発注精度の向上でロス削減) | ◎(期限把握で最大40%削減) |
| ROI(投資対効果) | 長期回収型(全社規模での最適化前提) | 短期回収型(即効性が高い) |
| 拡張性 | 高い(他システム連携・全社展開に有効) | 中~高(在庫・発注システムの補完として最適) |
統合システムは、在庫や発注を含む「全体最適」を担う強みがありますが、導入コストや期間が大きく、現場での運用が定着しにくい不安があります。
一方で、専用ツールは導入が容易で現場に即した仕様となっており、短期間で効果を発揮しやすいのが特徴です。
どちらを選ぶべきかは企業の方針次第ですが、「今すぐに現場の作業負担を軽減したい」「廃棄ロスを減らしたい」 という課題に対しては、専用ツールの導入が最も近道となるでしょう。
まとめ:賞味期限管理のための「専用ソリューション」という選択肢
統合システムは、在庫や発注を含めた全体最適を担う存在です。
一方で、賞味期限管理という“現場の日常業務”においては、必ずしも十分に機能しているとは言えません。
そこで有効なのが、賞味期限管理に特化した専用ソリューションです。
特に、次のような企業や店舗に最適です。
✅ 廃棄ロスをすぐにでも削減したい店舗
(食品ロス削減を経営課題として掲げている)
✅ 人手不足に悩んでいる店舗
(期限チェックに多くの人員を割けない/作業効率を上げたい)
✅ アルバイトや新人スタッフでも運用できる仕組みを求めている店舗
(属人化を防ぎ、教育コストを抑えたい)
✅ 既存の統合システムに満足しているが、期限管理だけは弱いと感じている企業
(統合システムを補完する目的で導入したい)
✅ 少人数で多品種を扱う業態(観光施設・空港・土産物店など)
(限られた人員で効率的に運営したい)
専用ツールは、導入コストを抑えつつ、現場で即効性を発揮できる点が大きな強みです。
また、統合システムと組み合わせて運用することで、「全体最適」と「現場最適」を同時に実現するという選択肢も。
👉 貴社にとって「賞味期限管理」が今なお現場の負担や廃棄ロスの要因になっているのであれば、ぜひ一度、専用ソリューションをご検討ください。
「Expiry Management(エクスパイリー・マネジメント)」は、賞味期限管理に特化したデジタルツールです。
商品ごとに賞味期限を入力するだけで販売期限を自動モニタリングし、期限が近づいた商品をスタッフへ即座に通知します。これにより、チェック作業の負担を大幅に軽減し、廃棄ロスの削減にもつながります。
この記事を書いた人
チーム賞味期限管理Labs
「チーム賞味期限管理Labs」は、賞味期限管理の最適化を考察するプロジェクトチームです。私たちのミッションは、小売店舗から食品ロスを削減し、持続可能なビジネス運営を実現するための効果的なソリューションを探求することです。このブログを通じて、私たちの知見や調査・研究成果を共有し、小売店様にとって価値ある情報をお届けしています。